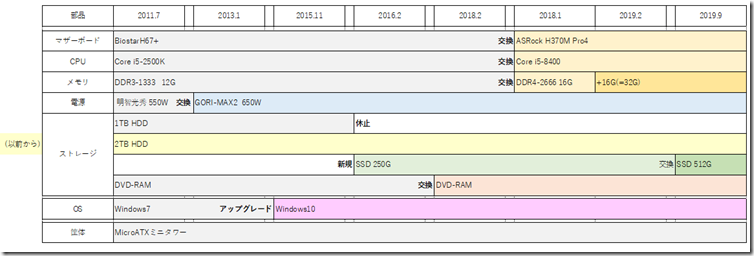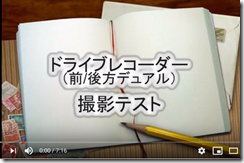Bluetooth密閉式のヘッドフォンマイク、配線の煩わしさがないのは良いのだが、装着するとアタリで耳が痛くなる。さらに周囲の音は聞こえなくなる…。そのため使用が限られていた。本当は常にお気に入りの楽曲やYouTubeの作業用BGMを聴いていたいのだが。
また、私は知りたがり屋なので、どんな環境でも音声検索をしたいと思っている。外出先や車の中ではスマホやタブレットでできていることが、ネットと一番相性の良いはずの自宅のPCでできないというのがなんとも歯がゆい。使っているchromeは音声検索ができるので、あとはマイクだけの問題なのだ。
上記2点の不満を解消するためには、ヘッドフォンマイクを身体から離して、常時使用できる環境を実現する必要がある。そこで写真のように、ヘッドフォンマイクを最大に拡げ、チェアの頭部を挟んでみた。互いの摩擦力で思ったよりしっかり固定されている。
これなら常に音楽を聴くことも、思いついたときに音声検索をかけることもできるようになった。うーん!この組み合わせは我ながらナイスアイデアですわ。
ちなみにBluetooth機器は、設定によっては,自動起動しない場合がある。うちのヤツもそうだったので、ググってみた。エレコムのHPの説明が分かりやすかった。「電源オプションのUSB設定の中にあるサスペンドを無効」にする必要がある。Bluetooth設定では無かったので今まで気づかなかった。
まぁしかしこれは常にバッテリが充電されているという前提である。うちでも常時USBから給電するための配線まではしたのだが、せっかくのBluetoothワイヤレス環境が、再び有線接続という状態になってしまった。これでは本末転倒である…。
そして、スピーカーとしてはたいへん使い勝手が良いのだが、web検索でマイクを使用しようとすると不便が。ヘッドレストに固定されたマイクに入力するためには、イスにもたれかかる姿勢となり、その結果、入力した文字の確認や検索結果などを表示する画面から目が離れてしまうことになるのだ。音声認識が100%完璧で、検索結果のうち必要な部分をすべて音声で返してくれれば良いのだが、そんなことは現状では不可能である。
ということで、けっきょくBluetoothヘッドフォンは、据え置きのマイクスピーカーとして使うこととなり、写真のような形で落ち着いた。こうなるともう、Bluetoothヘッドフォンである必要は無いのだが、新たな消費ではなく、今あるものを目的に応じた形で使うという意味では、満足である。